この記事の途中に、以下の記事の引用を含んでいます。
Demystifying a visual illusion: Why we see colour that’s not there
驚愕のイリュージョン!目に見えない色が脳内で生まれる現象とは?
私たちは日常の中で、たとえば強い赤色をじっと見つめた後に白い壁を見ると、緑や青など本来そこにはない色が浮かぶことがあります。
この現象は「色残像現象(カラーアフターイメージ)」と呼ばれ、不思議な体験として知られています。
今回ご紹介するのは、サウザンプトン大学のDr Christoph Witzel准教授らによる研究で、この色残像現象の“謎”が解き明かされた、という記事です。
長年にわたる専門家の議論を経て、ついに実証されたその結論――「“見えない色”を私たちが体験する、本当の理由」とは一体何なのでしょうか。
主張の核心!「色残像は反対色じゃなかった」――驚きの新データ
まず、記事の主張の核心部分を紹介します。
“We’ve finally got a conclusive answer – colour afterimages are not opposing colours as everybody had thought. Instead, those illusory colours reflect precisely what happens in the cone photoreceptors.”
(「ついに決定的な答えが出ました。色残像は従来考えられてきた“反対色”によって生まれるのではありません。実は、あの虚像の色は、目の中にある錐体細胞(コーンフォトレセプター)で生じている現象を、そっくりそのまま反映しているのです」)
従来、専門家の間では「色残像は神経回路が反対の色を表現するからだ」と信じられてきましたが、今回の記事は錐体細胞こそが主役である、と主張しています。
錐体細胞が起こす“身近で深い”錯覚――なぜ重要なのか?
この発見がなぜこれほど重要なのか、もう少し背景に踏み込んでみましょう。
まず記事では、私たちが昼夜を問わず同じ“赤”や“青”に見える理由の鍵も、こうしたメカニズムにあることが示唆されています。
“The cause of this illusion is the mechanism that allows us to see colours the same throughout the day, independently of light changes.”
これは、一日のうちに太陽や人工照明など光の質が絶えず変化しても、私たちが“色の恒常性(colour constancy)”を保てることと、色残像のメカニズムが密接に関係していることを示しています。
人間の視覚はただ物理的な色をとらえているのではなく、「環境適応」と「知覚調整」を絶えず行い続けています。
つまり色残像の根本的な謎を解明できないままでいると、色覚の全体像も正確に説明できません。
そのため、この研究が持つインパクトは、私たちの「色を見る能力」全体をより深く捉え直すポテンシャルを秘めているのです。
なぜこれほど長年“誤解”されたのか――心理的・神経科学的考察
研究では、従来定説だった「視神経系の信号処理が反対色を作る(例:赤のあと緑)」説や、「脳の奥深いどこかの未解明の機構が関与する」という説明を否定し、細胞レベルでの光刺激の順応=“錐体細胞での適応現象”を決定打としています。
“Across all the experiments, we found the same thing – afterimages are not caused by opposing colours, as many scientists have believed, Instead, they match what we’d expect if they were caused by how cone cells in the eye adapt to light.”
(「すべての実験で一貫して同じ結果が出ました。色残像は“反対色”によって起こるのではなく、“目の中の錐体細胞が光にどう順応するか”によって説明がつく、というものです」)
この見解自体は実は19世紀から提唱されてきたことでもありますが、色覚の情報処理は脳内処理、特に「中脳や視覚野での複雑な配線」こそ本質だ、という大勢の主流意見に押し流されてきました。
では、なぜこれほどまでに“色残像=反対色”説が幅を利かせてきたのでしょうか。
それは人間の色の知覚が直感的に“信号のリバーサル”に見えるからです。
たとえば「赤を見つめたあとは緑、黄色の後には青い残像が現れる」という経験自体が、「脳が反対色を作るに違いない」と直感させるためです。
しかし、今回の記事が強調するように、膨大なパラメータと精密な条件下で測定し直してみると、実はこれらの残像色は「理論的に想定される錐体細胞の反応スペクトルの変化」と一致する――つまり“目の最初の入り口”でほぼ決まっている、ということになります。
この結論が持つ意義は決して小さくありません。
色彩心理学、認知心理学ばかりか、映像工学やメディアデザイン、絵画、印刷、照明など「色に関わるすべての分野」で基礎理論の見直しが求められる可能性があります。
独自の視点!色残像現象は「脳の創造性」ではなく「生物の適応力」の証明か
この研究を受けて、個人的に特に興味深いと感じるのは「目のハードウェアの限界と、それを補うための生物進化の妙」です。
人間の網膜には光を感じる3種類の錐体細胞(赤・緑・青感受型)が存在し、それぞれが特定波長の光に強く反応します。
強い特定色に長く晒されると、その細胞は“適応”し、感度が一時的に下がる。
そこに無彩色(グレースケール)が現れると、順応しなかった他の錐体細胞が相対的に強く働いて「偽の色」を知覚する――理論としては極めて明快です。
近年のAI技術や画像認識分野でも、「色補正アルゴリズム」や「彩度自動調整」などの基礎として、ヒトの色適応の仕組みが数多く応用されています。
たとえば、スマートフォンのカメラの「ホワイトバランス自動調整」にも、網膜の色恒常性を模倣した技術が活かされています。
逆に、「反対色ルール」だけを前提にした処理だと、実際の人間の視覚とズレが生じてしまい、画面上の「残像」や「色被り補正」が正確にできず不自然な色になりがちです。
今回の記事で示された通り、「生物学的な順応」という最もプリミティブな現象こそが「美しい世界の色」の根拠であり、いわゆる「脳の幻覚」や「高度な脳内信号処理」はあくまで二次的な補助なのでは?とも考えられます。
また、この知見は「高齢者の色の感じ方」や「目の病気による色知覚の変化」といった“実生活の困りごと”の説明や改善策にも直結する可能性があるでしょう。
今後へのヒント――「見ている世界」の正体を問い直す
この研究から私たちが学べる最大の示唆は、「私たちが“見ている世界”も、脳が描き出す仮想現実である」という前提の中でも、驚くほど純粋な“生物的機能”が支えている事実です。
「色残像」という身近な現象も、つい根深い哲学や“脳の魔法”のように語られがちですが、実は私たちが“見る”ための根源的な仕組み――すなわち「光を感じて適応し続ける」という、ごく合理的な生体メカニズムの産物にすぎなかった。
今回の記事の発見は、「主観と客観の境界」「知覚の騙し絵」といったテーマに新たな視点を加え、われわれの色世界をより科学的かつ謙虚に見つめ直す気づきを与えてくれます。
今後の社会や科学技術において、「人間の目そのものがどのように環境に適応し、世界の色彩を構成しているのか」という問いがますます重視されるはずです。
カラーマネジメント、映像技術、アート療法、教育、さらには人間拡張(ヒューマン・オーグメンテーション)など、さまざまな領域で今回の知見が活用される日も遠くないでしょう。
categories:[science]
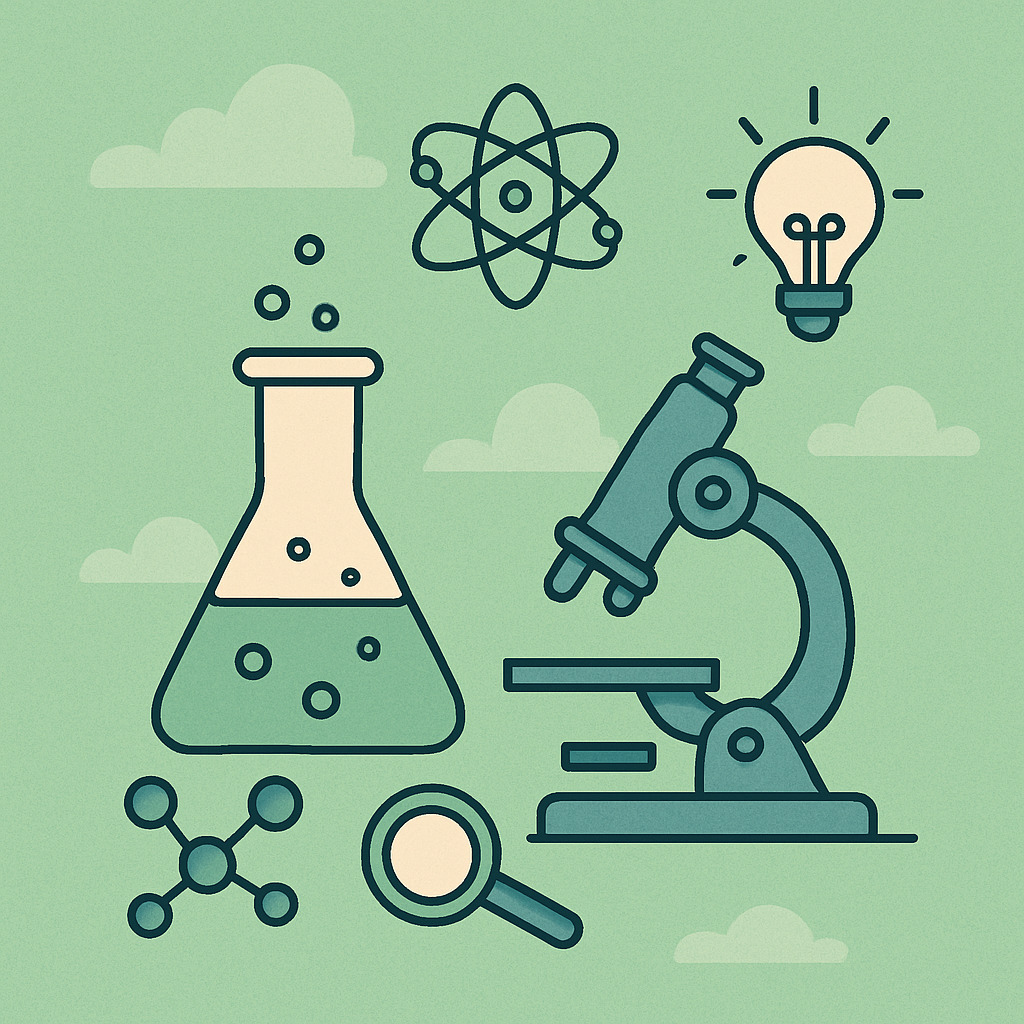

コメント