この記事の途中に、以下の記事の引用を含んでいます。
More than 30% of this century’s science Nobel prizewinners immigrated
科学の頂点を支える“移動”という現象
科学技術の進歩を決定づけるのは誰か。
それは優秀な科学者たちだというのは誰もが納得するところでしょう。
しかし、その“優秀さ”はどこで生まれ、どこで開花するのか──。
今回取り上げる記事は、2000年以降の科学分野ノーベル賞受賞者の3割以上が、生まれ故郷を離れて他国に移住していたという衝撃的なデータを基に、グローバルに流動する才能の実態と変わりゆく研究環境の今後を論じています。
ノーベル賞=その国の「勝ち」ではない。
この記事は、そんな素朴な想定を根本からくつがえす論点を提供してくれます。
データが語る:ノーベル賞受賞者の国境を超えた旅
まず記事では、次のような事実が挙げられています。
Of the 202 Nobel laureates in physics, chemistry and medicine this century, less than 70% hail from the country in which they were based when they were awarded their prize. The remaining 63 laureates left their country of birth before winning a Nobel prize, sometimes crossing international borders more than once, a Nature analysis shows.
つまり、今世紀に物理・化学・医学生理学で受賞した202名中、6割超の139名は「受賞時に在籍していた国で生まれ育った」一方、63名、すなわち約31%が移民だったというのです。
これは思ったより高い割合ではないでしょうか?
また、今年の化学賞では、3人のうち2人が移民。
物理学賞においても3人中2人が他国から移住した研究者だったと具体例が示されています。
なぜ移民研究者がノーベル賞を取るのか?──背景と意義を掘り下げる
世界のどこにでも「才能」は生まれるが、「機会」は偏在
記事では、マサチューセッツ大学のIna Ganguli教授の次の発言が紹介されています。
“Talent can be born anywhere, but opportunities are not,” says Ina Ganguli, an economist at the University of Massachusetts Amherst.
つまり、「才能はどこでも生まれるが、チャンスは均等とは限らない」。
この認識が、移民研究者がノーベル賞を受賞する背景を端的に物語っています。
例えば、1930年代にドイツからアメリカに渡ったアインシュタインや、ポーランドからフランスへ移住したマリー・キュリーといった歴史的な例も、こうした「才能の流動」によって科学の発展が加速された証拠です。
受賞者の“集積地”は変化したが、いまも米国が圧倒的
Of the 63 laureates who won the prize after moving out of their birth countries, 41 lived in the United States when their Nobel was awarded.
すなわち、移民研究者の“ほとんど”がアメリカでノーベル賞を手にしていることが分かります。
世界第二の「集積地」はイギリス。
しかしイギリス出身でも、より高給や地位を求めて国外に移る研究者も多いことが記事から読み取れます。
要するに、「知の流入国(主に米英)」と「知の流出国(例えば英独仏など)」との間で、グローバルな頭脳循環/偏在が続いているのです。
分野ごとにも移民率に差が
Among the science categories of the Nobel prizes, physics has the highest proportion of foreign-born laureates so far this century: 37%… chemistry at 33%, and finally, medicine at 23%.
理由として物理学の研究設備の高度さが挙げられており、装置が必要な物理では“場所”が大きな制約になることが暗示されます。
逆に医学分野は比較的「どこでもできる」ため、移民率が低いのです。
「知の国際競争」と移民規制──このままで科学は発展するのか
ここで注目すべきは、受け入れ国側の政策変化です。
The new analysis comes as the international flow of scientists and students faces growing obstacles. In the United States, for example, rampant grant cuts and stricter immigration policies… threaten a looming ‘brain drain’.
米国では研究助成金の予算カットに加え、移民政策の厳格化(H-1Bビザ申請1件で10万ドル!)が進んでいます。
カナダ、オーストラリア、イギリスでも留学生や外国人大学院生の受入れ制限が強化されつつあります。
知的人材流入で「科学大国」になったこれらの国にとって、この流れは自国科学への大きなリスクとなることは間違いありません。
これについて、カロライン・ワグナー(オハイオ州立大学)はこう警告しています。
Such restrictions “will slow the rate of highly novel research, period”.
つまり「極めて新規性の高い研究のペースが落ちる」というのです。
現場の実感でしょう。
論点・考察:移民は「才能流出」か「資源活用」か?
移民=自国の人材流出(ブレインドレイン)だとネガティブに捉えられがちです。
実際、日本でも「若手理系が海外流出」と話題になることが多いものです。
しかし、見方を変えれば、「世界のどこでも才能を爆発させるチャンスがある」環境の創出こそが科学全体の発展には不可欠です。
記事が繰り返し強調するように、才能は国境を持たない。
もし受け入れ国(特にアメリカ)が今後も移民規制・予算縮小を続けるなら、近い将来“頭脳の地殻変動”が起き、新たな科学の中心地が生まれる可能性もあります。
具体例を挙げれば、例えば中国はグローバル・タレント帰還プログラムを推進し、欧米で研鑽を積んだ研究者の“逆輸入”に積極的です。
ヨーロッパでも国境を越えた研究ネットワーク(EUのHorizon Europeなど)で、頭脳循環政策が重要視されています。
今後「ノーベル賞数=その国の力」なる単純なナショナリズム指標だけでは、科学立国の本質を見失う危険があるとも言えるでしょう。
結論──“国籍”ではなく“才能と環境”が科学を動かす
今回のNature記事が明らかにしたのは、21世紀の科学的トップの3割以上が「ふるさと」と「活躍の場」が異なる、という実態です。
これは単なるトリビアではありません。
「才能」は偶然世界中に生まれ、「機会」と「環境」を得て初めて歴史を動かす業績につながるという現実を、極めて端的に示したエビデンスです。
今後、世界どこでも才能にチャンスが開かれ、個人がベストな環境を得て大きく羽ばたける。
そんな社会システムこそが、ノーベル賞だけでなく、私たち全体の未来にとって重要なのだと本記事は強く示唆しています。
研究者、政策担当者、一般読者の方々も──「受賞した国」「生まれた国」という単純な物差しにとらわれず、「科学のために何が必要か」という視点を持つことがいっそう重要ではないでしょうか。
categories:[science]


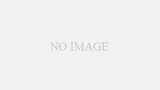
コメント