1. “たった1つ”のメモが生み出す圧倒的な自由
この記事は「append-and-review note(付加記録&レビュー式メモ)」という独自のノート術について、AI研究者として著名なAndrej Karpathy氏が自ら実践する方法を解説したものです。
私たちは仕事でも私生活でも、頭の中に様々なアイデアやTODO、ちょっとした疑問や気になる情報が次々と湧いてきます。
それらをどう管理し、活用していくのか。
多くの人が悩むテーマに対し、Karpathy氏は“最小労力・最大効果”をもたらす一つの答えを提示しています。
2. 「一筆メモ」が持つパワー――記事に見る主張
この記事の基本は非常にシンプルです。
ひとつのテキストノート(例えばApple Notesの「notes」1枚)だけを使い、思いついたことはなんでも上にどんどん追記するというやり方。
彼はこう述べています。
「ノートを複数管理し、フォルダや階層に分類するコストはあまりにも巨大な認知的負担になる。1枚のノートなら、CTRL+F(検索)がとても簡単で便利。」
—[引用元:https://karpathy.bearblog.dev/the-append-and-review-note/]
さらに、特にタグ付けや細かいメタデータ管理はほとんど行わず、「watch:」「read:」といった簡単なワードだけで十分だと断言しています。
最も大切にしているのはレビュー。
沈んでいく(古くなった)メモを時々読み返し、“注目すべき”と思ったらコピーして上に持っていく。
不要だと感じるものはそのまま「沈ませておく」。
この自然淘汰のサイクルが心地よいのだといいます。
3. 複雑なツールに頼らない――シンプル思考法の意義
この方法が面白いのは、「整理整頓しよう」「体系化しよう」という従来のノート術の逆を突いている点です。
多機能なノートアプリやToDoアプリ、データベースのようなツールが普及した今、自分自身の思考や情報も“構造化”しようとつい考えがちです。
でも、実際にはあれこれフォルダ分けしたり、タグ付けルールを作ったり、ノートカテゴリーを細かく分けた結果、「どこに書いたか分からなくなった」「分けたことに満足して手が止まった」という経験、誰もがあるでしょう。
Karpathy氏はそのカオス(混沌)を恐れません。
むしろ「何でも放り込んで、時が来たら振り返る」がベストだと考えているのです。
彼が挙げている例も生々しいほど日常感に溢れています。
たとえば…
- フィールドワークで思いついたアイディアを書き漏らさないため即座に1行追記。
- パーティーで誰かに「この映画見てみて」と言われたら、即「watch: 映画タイトル」を記録。
- 仕事中の一時的なコピー&ペースト置き場としても機能。
- 頭の中で膨らんだ考えを、一度ノートに「投げ捨てて」脳のRAMを空けて本業に集中。
この仕組みなら「忘れることへの不安」から解放されやすいのです。
つねに“思いつき”が書き込め、あとから自由に拾い直せるという安心感が、軽やかな生産性を生み出しています。
4. 今こそ立ち止まって考えたい:何が「記録」の本質なのか?
では本当に、このノート術が最強なのでしょうか?
当然、万能な方法はありません。
たくさんの“自分ルール”や独自タグ、あるいはデータベース型ノートアプリが合う人・場面もあります。
では、なぜ“1枚の追記式ノート”がここまで説得力を持つのでしょう。
主な理由は2つ考えられます。
(1)「検索できること」の凄さ
例えば、「そういえば去年の夏、旅行おすすめの本って何だったっけ?」とふと思い出したとします。
この方法なら、CTRL+F(もしくはスマホ検索)で「read:」や「summer」などのキーワードを入れるだけで瞬時に発見できます。
従来の階層構造ノートでは「どのフォルダだったかな…」と行き詰まることがありますが、検索一発で悩みが消えるシンプルさは圧倒的です。
(2)“沈めるメモ”と“浮かび上がるメモ”
人は、当初とても重要と思っていたことが、時間が経つと関心が薄れることがあります。
逆に、数年前の「とりあえずメモ」が今になって新たな発見に繋がることも。
「レビュー」によって、本当に大事な情報だけを上に昇格させるこのサイクルは、人間の思考の自然淘汰プロセスとも言えます。
組織やプロジェクトにおいても、膨大なアイデアのなかから価値あるものを“救出”する作業は必須です。
個人の情報管理でも同様で、都度の選別・編集機会を持てるこの方法は、情報との付き合い方自体を見直させてくれます。
私の見解:情報の“進化”を促す感覚
私自身、様々なノートアプリやツールを遍歴してきました。
一時はビジュアルノートや階層フォルダ、中にはカード式メタデータツールなど、盛りだくさんの試行錯誤をしたこともあります。
そのすべてが悪かったとは思いません。
しかし、積み上げ式1枚ノートのシンプルかつ自由な流れは、「何を書いてもいい」「後戻りしてもいい」という心理的ハードルを徹底的に下げてくれることを実感しました。
また、メモが“過去の自分”とつながるタイムカプセルになり、雑多な発想こそ自分の個性になっていく。
その積層こそが、知的資産だと実感するようになったのです。
考えをまとめる暇がないときも、とにかく書き出して、後でじっくりレビューする。
これだけで“置き去り”の不安からかなり解放されます。
「整理すればするほど逆に思考が停滞する」人や、「立派なノートを作らねば」と思って記録が滞りがちな人にも、この方法は間違いなく役立つでしょう。
5. 今日から始めるためのヒント――あなたの情報管理への示唆
この記事は「メモの本質は“分類”や“仕分け”にあるのではなく、“思考を吐き出し、後日面白さを発見する自己対話”にあるのだ」と改めて気づかせてくれます。
その核心は、道具ではなく“やり方”にあります。
スタートの一歩
- まずどんなアプリでもいいので、「notes」や「メモ」などシンプルな1枚テキストの場を作る
- とにかく追記、追記
- 全てを残す必要なし。時々思い立ったときに軽く流し読みして、面白い・重要だと思うメモはコピペで上に持ってくる
- ルール化やラベリングしない(やりすぎない)。必要最小限のキーワードだけ
もし「情報の沼」で溺れていると感じたら、ぜひ一度この“append-and-review note”を試してほしいと思います。
1枚のノートが、あなたの人生を支える「心の外部メモリ」になるかもしれません。

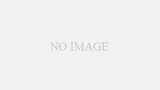

コメント